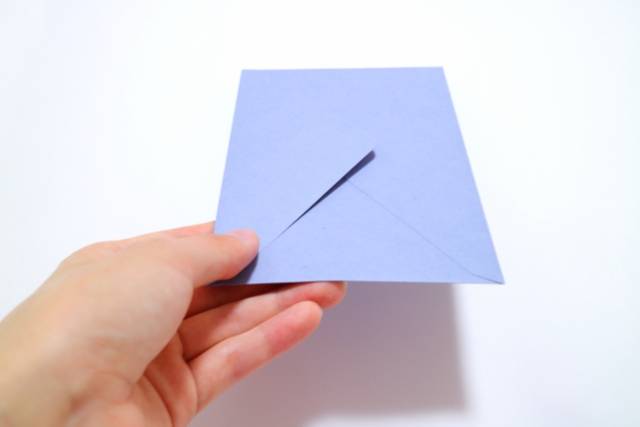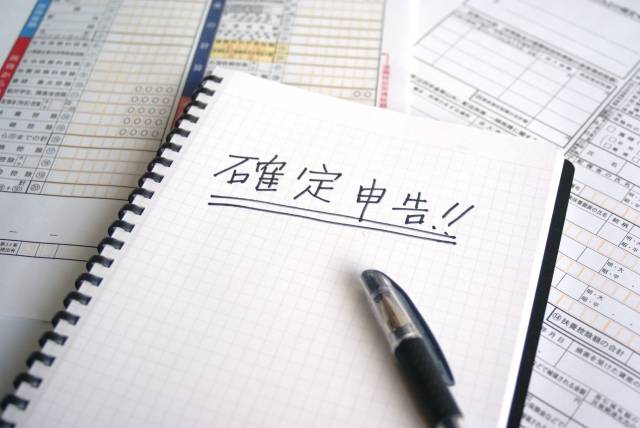年功序列の会社も少なくなってきて働いていても、給料が上がらないと嘆いている人も多いでしょう。
同世代の他の人がどのくらいの年収があるか気になりますよね。
年収300万円は他の人と比べて多いのでしょうか?
実は、年収が300万円以上400万円以下の人は、給与収入者全体の17%を占めており、最も高い割合を占めています。
年収300万円でも、うまくやりくりをすれば欲しいものが買えたり貯金もできます。
その為には、家計から出ていく支出について考えていくことが必要です。
節約や節税の知識があるだけで、手元に残るお金が増えて貯金にまわすこともできるのです。
年収300万円とは実際にどれくらい貯金ができるか、将来結婚や家は購入できるのかの不安についてお答えします。
年収300万円の人の割合

国税庁による「民間給与実態調査」によると、年収が300万円超、400万円以下の人口は約890万人で全体の17% ほどを占めています。
100万円毎に分けた給与階級分布で比較してみると、全体でもっとも高い割合を占めたのが年収300万円台です。
過去5年分のデータを比較してみても年収300万円超、400万円以下の方の割合は17% 前後で推移しており、もっとも多いという結果なのです。
また、「300万円以下」「200万円以下」「100万円以下」を合計すると、37%になります。つまり、給与所得者(非正規雇用を含む)の4割が、年収300万円以下です。
年収300万円台は、標準的な収入の額だと考えることができるでしょう。
年収300万円の手取り月収

年収の中には、税金や保険料などが含まれているため、全額が手元に残るわけではありません。
年収300万円とは具体的にどれくらいの手取りになるのでしょうか。
会社員の場合
会社員の場合には、所得税や住民税、厚生年金保険料と健康保険料などが給料から自動的に天引きになります。
年収300万円の場合には、所得税が約6万円、住民税が約12万5000円程度かかり、税金で18万5000円になります。
厚生年金保険料と健康保険料を合算した社会保険は、年間で約42万円かかるので、60万円程度年収からひかれることになります。
年収300万円から税金と保険料を差し引いていくと、手元に残るのは230万〜240万円ほどになり、手取り月収は20万円前後になる方が多いでしょう。
ボーナスを含めた年収の場合には、月収がさらに少なくなるので、240万円から平均ボーナス額約40万円を差し引いた200万円を12分割した16.5万円程度ということになります。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、経費を引いた額を算出し、そこから保険料や税金が差し引かれます。
例えば、年収が300万円で仕事にかかった経費が100万円なら、200万円が所得として計算されます。
税金は、所得税は約3万1000円、住民税においては7万2000円程度かかるので、年間10万3000円になります。
国民健康保険料は年間約15万円で、国民年金保険料は19万円ほどなので、年間44万円程度かかります。
月収で割ると、21万3000円程度になりますが、個人事業主の場合には、仕事で使うものとプライベートで使うものを、経費按分することができます。
例えば、携帯電話やパソコンを仕事で使う場合には、仕事で使う分と、プライベートで使う分を割合で分けることによって、購入代金や、毎月の使用料を経費として計上することができます。
毎月1万円の携帯電話料金の支払いの場合、仕事で使う割合50%、プライベートで使う割合50%という按分をすれば、通信費として経費の計上ができるので、個人の支出を抑えることができます。
年収300万円で貯金は可能なの?

年収300万だと生活はなかなか厳しいと思っている人も多いかもしれませんが、少しの工夫や節約に目を向けることで、無理なく暮らすことは可能です。
会社員の年収300万円の手取りはおよそ240万円、月の手取りで換算すると約20万円ですが、月収20万円ほどで、貯金はできるのでしょうか。
月々にかかる費用には、大まかに以下のものが挙げられます。
・食費
・家賃
・水道光熱費
・通信費
・その他(交際費・趣味・日用品・交通費・衣類など)
貯金をする際に大きく関係するのが家に関する支出です。
家賃は年収の約3分の1が平均相場と言われており、年収300万の場合は、家賃は6万円前後が理想です。
家賃6万円だった場合に、残り外を14万円で、いくらほど貯金ができるのでしょうか。
一人暮らしの場合、夫婦二人の場合、夫婦二人・子供一人の場合の場合で比較してみましょう。
一人暮らしの場合
| 食費 | 50,000円 |
|---|---|
| 家賃 | 60,000円 |
| 水道光熱費 | 10,000円 |
| 通信費 | 10,000円 |
| その他 | 30,000円 |
| 合計 | 160,000円 |
この場合の貯金可能な金額は4万円です。
一人暮らしの場合には、外食が多くなる人が多いので食費に関しての支出が高めになります。
自炊をするならば、食費は3万円くらいにおさめることができるでしょう。
② 夫婦二人の場合
| 食費 | 40,000円 |
|---|---|
| 家賃 | 70,000円 |
| 水道光熱費 | 10,000円 |
| 通信費 | 20,000円 |
| その他 | 30,000円 |
| 合計 | 170,000円 |
この場合の貯金可能な金額は3万円です。
二人暮らしということで、家賃は一人暮らしより高めになります。
食事を自炊にすれば、二人の場合でも食費を抑えることができます。
自由に使えるお金は一人の場合よりも少なくなります。
③ 夫婦一人・子供一人の場合
| 食費 | 50,000円 |
|---|---|
| 家賃 | 70,000円 |
| 水道光熱費 | 10,000円 |
| 通信費 | 20,000円 |
| その他 | 40,000円 |
| 合計 | 190,000円 |
この場合の貯金可能な金額は多くても1万円前後でしょう。
子供が増えるとかかる費用が多くなるので、貯金するのは厳しくなります。
しかし、国からの児童手当、会社からの手当てがある会社もあるので年収が上がる為、その分を貯金に回すことはできます。
年収300万で結婚できる?

先ほどのシュミレーションで考えても、年収300万円で結婚しても、贅沢をしない限り生活はできるので結婚はできます。
共働きであれば、収入は増えますので、無駄な買い物をしなければ貯金はちゃんとでき、たまに旅行へ行くことも出来ます。
子どもがでたときには、生活環境が変わるので、子供がいないうちに貯金をしておく必要があります。
現在貯金がない状態で、手取り月収が20万円であれば、教育費の貯金は毎月2〜3万円くらいしておくべきです。
高校と大学にかかる大まかな費用は、以下の通りです。
高校に通うまでの15年間、毎月2万円貯金していれば、約360万円貯まります。
高校と大学にかかる大まかな費用は、以下の通りです。
| 高校(3年間) | 大学(4年間) | |
|---|---|---|
| 公立 | 115万円 | 240万円 |
| 私立 | 290万円 | 390万〜520万円 |
私立に通わせるのは、厳しいですが公立に通えるくらいの金額は、貯金をしておく必要があります。
結婚式費用について
国内挙式、海外挙式、身内だけの挙式、友人たちも広く呼ぶ場合など、パターンは様々ですが平均250~300万円の費用がかかるのが一般的です。
また、婚約指輪・結婚指輪なども大きな出費で、平均では40-50万円です。
ご祝儀や、ご両親からの援助金など頂くことを考えると実質の持ち出し金額は減ることになりますが、新婚旅行の旅費も含めて、合計で350~400万円必要になるので、結婚式は親族のみで新婚旅行も近場でという夫婦も増えています。
年収300万円で家は買える?

支出で一番大きいのが住居にかかる費用です。
賃貸で家賃を払い続けると、将来の資産になるものがなく、一生家賃を払い続けることになります。
そこで、話題になるのが、家を購入するべきかどうか。
家を購入するには、大きなお金が必要になるのでローンを組む方がほとんどです。
家を買うときに借りられる住宅ローンは、年収の5〜6倍が目安です。
年収300万円の場合、1,500万〜1,800万円まで借りられます。
それ以上となると、月々の返済に追われて生活が苦しくなる可能性があり、審査が通らないこともあるので、頭金を多く出すか、予算内で物件を探す必要があります。
頭金はなくてもローンを組むことはできますが、借りるお金が多いほど月々の返済金額が増えるので、頭金はあったほうがいいです。
また、頭金をためてローンを組み、そこからローンを返済していくとして、返済期間が30年の場合、毎月5〜6万円ほど返済しなければいけません。
家賃を払い続けるよりも資産として残るのでおすすめですが、無理なローンは組まないようにご注意ください。
おすすめ節約方法
年収300万円で暮らすためには、節約が大事になります。
無駄な出費を抑えるためにできる、食費、通信費、水道・光熱費関する節約術について解説します。
食費
食費は外食を減らしたり、工夫次第で出費を抑えることができます。
以下のことは意識するだけでかなり出費を抑えることができるので実践しましょう。
- 自炊を心がける
- コンビニの利用はしない
- ペットボトルを購入しないようにマイボトルを持ち歩く
- 食材をまとめて買うようにして無駄買いを防ぐ
通信費
通信費は知っているだけで簡単に節約ができます。
月々の携帯料金が1万円を超えている場合は、以下のことで固定費を抑えましょう。
- 格安SIMに切り替える
- 契約プランを見直す
- 固定電話が必要ない場合は、光回線などではなくポケットWi-Fiなどを活用する
水道・光熱費
水道・光熱費を抑えるポイントは以下になります。
- ガスや電気の料金プランの見直し
- 洗濯の際に風呂の残り湯を再利用する
- 家電の買い替えの際にエコ家電を購入する
水道・光熱費を抑えるためには、まずガスや電気の料金プランを見直してみましょう。
ご家庭にあったプランに変更することで、年間数万円もの節約になることもあります。
ふるさと納税を活用する
税金を減らすことが、手取りの金額を増やす方法です。
おすすめの節税対策は「ふるさと納税」で寄付のうち2,000円を超える部分は所得税の還付や住民税の控除が受けることができます。
返礼品としてその地域の名産品がもらえるので、生活に役立つお米や食品を選べば生活費を節約できます。
ふるさと納税の上限額は年収によって決まっています。
年収300万円の方の場合の限度額の例は以下の通りです。
| 独身または共働き | 28,000円 |
| 夫婦または共働き+子ども1人(高校生) | 19,000円 |
| 共働き+子ども1人(大学生) | 15,000円 |
| 共働き+子ども1人(高校生) | 11,000円 |
| 共働き+子ども2人(大学生+高校生) | 7,000円 |
| 夫婦+子ども2人(大学生+高校生) | 0円 |
ふるさと納税は初心者でも簡単にできます。
副業で年収アップ
年収を上げる方法は、転職があります。
転職によって年収をアップすることができる可能性はありますが、いきなり現在の仕事をやめて職探しをするとなれば、当然リスクが伴います。また、転職に成功したからといって確実に年収がアップするという保証もありません。
リスクを低くして年収をアップする方法が副業です。
空いた時間を使ってはじめることのできるネット副業なども増えています。
大幅に年収を増やせるとは限りませんが、副業でおこずかいを稼ぐことができれば、自分の趣味に使えるお金も増えます。
副業による収入が20万円をこえた場合には、確定申告をする必要があります。
確定申告によっては、収めた税金が還付されることもありますので、税金のことを知っておけば節税に繋がります。
まとめ
年収300万円以下でも、少し節約や工夫に力を入れれば無理なく暮らすことができます。
結婚や持ち家の購入もできるでしょう。
各種手当の給付を受けたり、節約、節税をを心がけて、少しでも余裕を生み出しましょう。
この記事は私が書いたよ!
sakura
こんにちは、sakuraです。サイトを訪れてくださり、ありがとうございます。最新のトレンド、有益な知識、そして日々の生活に役立つ情報を提供させていただきます。このサイトを通じて、皆さまの生活に有益な情報をお届けできるように頑張ります。